大和国内は南北朝の動乱以降、国人同士の争いが絶えず、領土の奪い合いは日常茶飯事でした。
しかし、支配地の移動はあくまで興福寺・春日大社の衆徒・国民間の中だけに限られてきました。
しかし1497(明応6)年、畠山尚順は敵対する畠山義豊に与した大和国人・万歳氏、布施氏の領地を攻め取ると、闕所となった両氏の所領を配下に与え、他国衆による大和への侵略は、興福寺と大和国人たちに大きな衝撃を与えます。
そして1499(明応8)年に始まる細川政元被官・赤沢朝経による大和侵攻を目前にして、ついに南北朝時代以来の宿敵同士である筒井氏、越智氏が同盟。
赤沢朝経に与した古市氏を除くほぼすべての大和国人が一揆を結んで他国衆に対抗します。
大和国人一揆は団結して赤沢朝経率いる京衆に立ち向かいましたが、2度に渡る侵攻は京衆の勝利に終わり、1506(永正3)年に国中(くんなか=奈良盆地)一帯は赤沢朝経の支配下に入りました。
しかし、赤沢朝経による大和支配は、翌1507(永正4)年、細川京兆家の後継者争いに端を発した永正の錯乱により、突然の終焉を迎えるのです。
永正の錯乱
1507(永正4)年6月23日、畿内を制覇して半将軍とも称され、権勢の絶頂にあった細川京兆家の総帥・細川政元が、内衆の薬師寺長忠、香西元長らによって自邸で入浴中に暗殺されました。
この暗殺の背後にあったのが細川京兆家の家督問題に端を発する家臣団の分裂です。
権謀術数を尽くして敵対勢力を打ち破り、将軍すら挿げ替えた政元は優れた政治家であり武将でしたが、若年の頃から修験道に没頭して女性を近づけなかったため実子がいなかったため、三人の養子を迎えていました。
摂関家の九条家出身の澄之、阿波守護家出身の澄元、そして京兆家分家・野州家出身の高国の三名です。
混乱の始まりは1503(文亀3)年、政元が前年正式に嫡子と定めた澄之を突然廃嫡し、澄元に家督を譲ると突然決めたことでした。
1506(永正3)年、澄元は摂津守護に任じられると、地元の阿波勢を引き連れ入京。
とりわけ阿波守護家の重臣であった三好之長は知略と武勇に優れた人物で、政元にもその武勇を見込まれて重用されました。

この三好之長こそ、後に畿内の覇者となって将軍を京都から追放した三好長慶の曽祖父であり、三好氏が畿内に勢力を扶植するのはまさにこの時からです。
之長は応仁の乱中には畿内で土一揆を扇動した他、数度にわたり主家に対する裏切りを繰り返した一筋縄ではいかない灰汁の強い人物でしたが、都度その武略を惜しまれて帰参し、持ち前の上昇志向で武功を重ね、阿波守護家で重きを成しました。
三好之長は京兆家に仕えるようになってからも、猛将・赤沢朝経らと協力して畿内の反細川勢力を打ち破り、短期間のうちに武功を重ねます。
赤沢氏、三好氏ともに信濃源氏・小笠原氏の諸流という共通の出自を持ちますが、何より外様衆の両者は実力と実績で地位を上昇させる他なく、共にあくなき上昇志向を持って畿内に活躍の場を求めたのでしょう。
三好之長を中心とする阿波衆が細川京兆家内での存在感を高めるにつれ、元々京兆家重臣で畿内有力国人層が中心の内衆との対立を深めていきました。
このまま澄元が京兆家の家督を継げば阿波衆がますます台頭し、本来の京兆家重臣であった内衆の立場が危うくなると考えた薬師寺や香西は、廃嫡された澄之を擁して政元を暗殺し、三好之長の排除に動いたのです。
政元暗殺の翌6月24日には澄元、三好之長らが屋敷を襲われ近江へ逃亡し、クーデターを起こした薬師寺、香西に擁立されて澄之が京兆家の家督を継ぎました。
また、この政変で6月26日には丹後遠征中の赤沢朝経が撤退に失敗して自害し、朝経を通した細川京兆家の大和支配は唐突に終焉を迎えます。
しかし、一部の内衆によるクーデターは細川一門の支持を全く得ることができませんでした。
おそらく細川氏と血統上の繋がりがない澄之が、細川氏の宗家・京兆家の家督を継承することは、もとより他の一門衆の支持を得られていなかったのでしょう。
政元による突然の澄之廃嫡と澄元後継指名も、細川一門衆の働きかけによるものだったのかもしれません。
こうして澄之派は孤立し、8月1日には澄元方の反撃に遭って細川澄之、薬師寺長忠、香西元長らは討死を遂げました。
翌8月2日には細川澄元が将軍・足利義澄に謁見して、正式に京兆家家督を継ぎ、あっけなく京兆家内衆によるクーデターは収束したのです。
赤沢長経の大和侵攻
赤沢朝経が永正の錯乱で自害したため、6月末までに京衆によって領地を追われた大和国人たちが次々と旧領に復帰していく中、朝経の養子であった長経は従軍していた丹後遠征から無事帰還を果たし、細川京兆家当主となった細川澄元に改めて仕えました。
8月になって永正の錯乱による混乱が収束すると、長経は再び養父が制圧していた大和の奪還に向けて動き出します。
8月27日には、長経が大和の再侵攻に向けて動き出していることが奈良まで伝わると、大和国人一揆は再び団結し、9月に入ると河内の畠山尚順(尾州家)、畠山義英(総州家)が大和へ使者を派遣し、両畠山家と大和国人一揆が連携して細川京兆家に対抗していくことで合意しました。
9月に入るといよいよ赤沢長経率いる京衆は大和を目指して南下を開始し、9月10日には木津、狛(以上、現京都府木津川市)、祝園(現京都府精華町)に布陣。
古市氏も大和へ迫る京衆と連携する動きを見せます。
これに対し、大和国人は十市遠治を始め、箸尾氏や南方衆(南和の国人たち)が奈良に入り、筒井勢は郡山、そして同年急死した越智家令の子で越智氏新当主となった越智家教(春竹)が、筒井(現大和郡山市)へ入って京衆の襲来に備えた他、河内からは畠山氏の援軍が生駒山を越えて大和へ入りました。
両軍は大和、山城国境で睨み合いを続けましたが、10月6日に大和国人衆が相楽郡の京衆へ攻撃を加え戦端を開きます。
戦闘が本格化する中、10月12日に畠山氏重臣の遊佐氏が生駒を越えて大和へ入り、大和国人衆とともに相楽郡に展開した京衆を挟撃する構えを見せると、細川澄元が自ら山崎(現京都府大山崎町)付近へ出陣。畠山氏を牽制する動きを見せます。
すると、細川京兆家との直接対決を恐れた畠山氏はぴたりと動きを止めてしまったのです。
赤沢長経はこの好機を見逃さず、古市勢も加わった京衆は奈良街道を南下して般若寺付近へ進撃。

古来より幾度も山城・大和国境付近での戦いの舞台となった
京衆主力は赤沢長経と三好之長の弟・三好越後守(勝時)と丹波衆、そこに古市澄胤の兵が加わっていました。
ちなみに三好越後守は、戦国時代に活躍した三好三人衆の一人、三好宗渭(政康)の祖父にあたる人物です。
これに対し、大和国人衆は筒井順賢、十市遠治、箸尾為時、楢原氏らが迎撃しましたが防衛線を突破されて敗走。
奈良へ乱入した京衆は瞬く間に櫟本(現天理市)付近まで進出し、10月20日には赤沢長経が番条(現大和郡山市)に入って陣を固めると、筒井順賢、成身院順盛らは畠山氏を頼って河内高屋城へ逃亡。箸尾為時は堺、十市遠治は河内の太子、越智家教は下渕(現大淀町)へと、大和国人衆たちは領地を離れて国外や吉野に身を隠しました。
しかし、11月13日になると逃亡先で体勢を立て直した大和国人衆は、二上山、三輪山と現在の天理市東部の山間地域である釜口、桃尾で一斉にかがり火を焚いて気勢を挙げます。
奈良盆地各地に展開していた京衆はこれを見ていったん奈良まで撤退すると、筒井、十市勢は高田城(現大和高田市)に入って反撃の姿勢を見せましたが、11月15日には京衆によって生駒、矢田(現大和郡山市)、松尾(現大和郡山市)をはじめとした各地の拠点が悉く焼き払われ、高田城の大和国人衆は宇智郡(現五條市)へと逃れました。
こうして大和の平野部一帯は赤沢長経の手に落ち、再び大和国人一揆は京衆の侵攻の前に敗北したのです。
永正の大和国人一揆崩壊と赤沢長経の最後
永正の錯乱から赤沢長経による大和侵攻の間、畿内と西国の状況は目まぐるしく動いていました。
細川政元の横死後、幕府は西国一の守護大名・大内義興を頼って周防に逃れていた前将軍・足利義尹の動向を警戒し、1507(永正4)年閏6月に義尹を庇護する大内義興の討伐令を出します。
しかし、大内義興は混乱する畿内の情勢を見て好機と考えたのでしょう。
逆に義尹を擁した義興は周辺諸国に呼びかけて上洛軍を起こし、備後鞆まで進軍して入京の機会をうかがいました。
一方、畿内では三好之長が澄元から政務を一任されて幕政を主導しましたが、摂津・丹波の国人層を中心とする旧来の細川京兆家重臣たちとの対立がいまだにくすぶったままで、之長の専横に反発する細川家重臣たちは、政元のもう一人の養子であった高国のもとに集まり始めます。
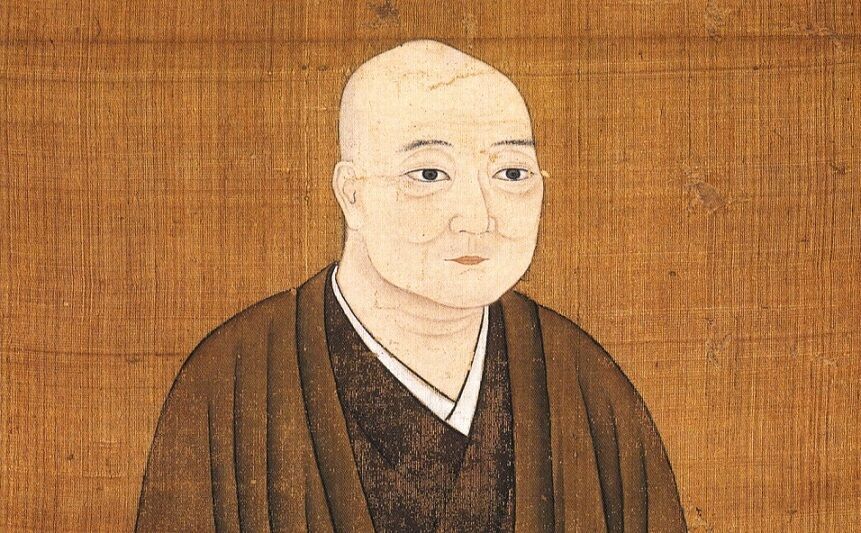
このような情勢下で河内では同年12月、再び畠山尚順(尾州家)と畠山義英(総州家)の抗争が再燃すると1504(永正元)年以来続いた両家の和睦が破られました。
両畠山氏和睦の破綻によって大和国人一揆も解消の方向へと向かいます。
応仁の乱以前より続く尾州家と筒井党、総州家と越智党の関係は、ここに至っても断ち切りがたいものがあったのでしょう。
12月10日に畠山尚順は細川澄元と和睦すると、細川高国、赤沢長経、そして筒井党が主力とみられる大和国人衆の援軍と合流し、畠山義英の籠る嶽山城(現大阪府富田林市)を攻め、翌1508(永正5)年正月に嶽山城を陥落させました。
しかしこの時、畠山尚順の勢力伸長を危惧した赤沢長経は、義英を逃がしたうえで尚順とその義弟・細川高国(尚順の妻は高国の姉)に叛意ありと主君・澄元に讒言したことから事態が複雑化します。
細川高国は、身の危険を感じて伊賀へと出奔すると、備後まで進出していた足利義尹、大内義興と結び、細川京兆家の有力被官であった摂津国人・伊丹元扶、丹波守護代・内藤貞正らの支援を取り付けることに成功。
ここに再び細川京兆家は分裂し、二人の将軍をそれぞれ擁して対峙する事態となったのです。
同年4月、ついに大内義興が足利義尹を奉じて上洛を開始すると、細川高国と丹波、摂津の国人衆や畠山尚順もこれに呼応する動きを見せ、将軍・足利義澄、細川澄元は防ぎきれないと考えたのか京都を放棄。近江へと逃れました。
細川高国、畠山尚順に堺で迎えられた義尹は、6月に1493(明応2)年6月以来15年ぶりに入京を果たすと、7月1日に再び将軍に復位します。
こうして義尹は日本史上唯一、将軍への復位を果たした人物となりました。
この段階で、足利義澄と義尹をそれぞれ擁する両細川氏の陣営は下記の通りで、畿内は細川京兆家の家督を巡る争いが1532(天文元)年まで、20年以上も続くことになります。
| 将軍家 | 足利義澄(11代将軍) | 足利義尹(10代将軍) |
| 細川京兆家 | 細川澄元 | 細川高国 |
| 細川家臣 | 三好之長(阿波衆) 赤沢長経(外様衆) |
伊丹元扶(摂津国人) 内藤貞正(丹波守護代) |
| 畠山家 | 畠山義英(総州家) | 畠山尚順(尾州家) |
| 守護大名 | ー | 大内義興 |
| 大和国人衆 | 古市澄胤 越智家教 |
筒井順賢 十市遠治 箸尾為時 |
この対立の図式を見ると、戦国後期の三好氏・松永氏による大和侵攻に繋がる因縁が、この時期に形成されたように見えますね。
また、明応の政変以降、畿内では政治の混乱が続き、幕府が全国政権として全く機能不全に陥っており、全国に戦国の争乱が広がるのもむべなるかなと言えるでしょう。
足利義澄、細川澄元が近江に脱出したものの、赤沢長経は意気軒昂で、筒井順賢から奈良を奪回すべく再び奈良へ侵攻します。
7月19日に赤沢長経は古市澄胤とともに奈良になだれ込むと、筒井順賢、十市遠治、箸尾為時らが迎撃しましたが、三条通、大安寺の防衛線を相次いで突破され、多くの戦死者を出して敗走しました。
敗走した筒井党は7月24日には河内片野の極楽寺城(現大阪府枚方市)まで撤退し、その後、若江城(現東大阪市)へ移動。
さらに翌7月25日には河内国を2日間で30Kmほど北から南へ縦走する強行軍で、筒井党は高屋城(現大阪府羽曳野市)を攻め落として入城します。
これを追って赤沢長経、古市澄胤は7月26日に、筒井党が籠る高屋城に攻め寄せましたが、高屋城へ打ち寄せる赤沢勢の背後を、京都から出陣した畠山尚順の軍が急襲します。
高屋城の筒井党と背後の畠山尚順勢から挟撃された赤沢勢は、多くの戦死者を出して壊滅。
赤沢勢の主だった武将が次々に戦死する中、赤沢長経は戦線を離脱して大和へ逃亡しましたが、古市澄胤はついに逃げ切れず自害に追い込まれます。
他の国人たちとは一線を画した動きを取り、興福寺すら裏切って自身の利益を最大化しようとした大和武士随一のトリックスター・古市澄胤は、河内で敢え無い最期を遂げました。
その後7月28日に赤沢長経は初瀬(現桜井市)で捕縛され、8月2日に河内で斬首となります。
こうして大和国人にとって最大の脅威となった赤沢朝経・長経父子による大和侵攻は、終焉を迎えました。
しかし、赤沢長経が世を去った後も、将軍位を争う足利義澄、義尹、細川京兆家の家督を争う細川澄元、高国の戦いはその激しさを増し、この畿内の争乱に連動しながら再び大和国人は二派に割れて激しい闘争を続けることになるのです。

![応仁の乱 戦国時代を生んだ大乱 (中公新書) [ 呉座勇一 ] 応仁の乱 戦国時代を生んだ大乱 (中公新書) [ 呉座勇一 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4015/9784121024015.jpg?_ex=128x128)