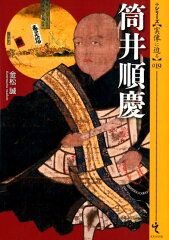皆さんこんにちは。
筒井順慶という戦国武将がいます。
大和国(現奈良県)の国人領主の出身で、戦国きっての梟雄・松永久秀と大和国の覇権を争った順慶は、最終的に久秀に勝利して大和一国の守護に上り詰めた人物です。
しかし、順慶の名は一般に、「洞ヶ峠の順慶」として広まりました。
本能寺の変に際して大恩ある明智光秀を裏切り、山崎の戦いでは日和見を決め込んで参加せず、最終的に勝ち馬の羽柴秀吉についたとされ、「優柔不断な狡い武将」という負のイメージが、以後つきまとうことになってしまいました。
一方、順慶とともに光秀の有力組下大名だった細川藤孝も、姻戚関係にある光秀に味方しなかった点では順慶同様ながら、本能寺の変後の動きについての評価は、順慶に比べて随分高いように思います。
しかし、本能寺の変直後の畿内の情勢を考えたとき、筒井順慶の立場は極めて重要なものであり、史実を追うと順慶はあまりに過小評価されている武将であるとわかります。
結論から言うと、順慶は山崎の戦いの結果に、最も大きな影響を与えた武将の一人でした。
⇒U-NEXTで筒井順慶も登場する『麒麟が来る』を視聴するならこちらをクリック!※本ページの情報は2022年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。 ![]()
本能寺の変のあらまし
1582(天正10)年6月2日、京都本能寺で天下統一目前だった織田信長・信忠親子は、重臣明智光秀の謀叛により死亡します(本能寺の変)。
当時、羽柴秀吉は備中国で毛利と、柴田勝家は越中国で上杉と、滝川一益は上野国で関東平定にあたり、丹羽長秀は信長三男の信孝とともに大坂で四国出兵の準備中で、本能寺の変は京都周辺の軍事的空白を衝いた光秀の造反劇でした。
織田家中で謀叛人となった光秀が味方になってくれるよう大きく期待したのが、自身の有力な組下大名(指揮下にあった大名)だった大和国18万石の筒井順慶と、丹後国11万石の細川藤孝です。
この両大名は、光秀の組下大名だっただけでなく、個人的にも深い関係にありました。
まず順慶にとって光秀は、自身を織田家中に取り次いでくれた人物であり、順慶が織田家傘下となった後も、順慶の大和支配や織田家での身の処し方など、陰に陽に協力や便宜を図ってくれた人物になります。
順慶にとって、大和国の覇権を争う松永久秀との抗争を勝ち抜き、大和守護の地位を確立するうえで大変な恩人でした。
一方の藤孝にとって光秀は、ともに最後の足利将軍・足利義昭の家臣時代からの知己であり、嫡男忠興の舅だったのです。
しかし、両者とも最終的に光秀に味方することなく、本能寺の変からわずか11日後の6月13日、山崎の戦いで光秀は秀吉に敗れ、逃亡中に命を落とすことになります。
この時、順慶は当初光秀に協力的な動きを見せつつ、最終的には秀吉に味方する意思を示したものの、山崎の戦いへ参加しなかったことから「日和見大名」の誹りを受けることになりました。
その一方で藤孝は、本能寺の変後まもなく髻を落として信長への弔意を示したことから、これがいち早く秀吉へ味方する姿勢を見せたと評価され、光秀に味方する勢力を減らして、秀吉の勝利に大きく寄与したと、後世まで高く評価されることになります。
順慶も藤孝も最終的に関係の深い光秀を見限った点で共通するのに、この大きな評価の落差は、はたして妥当なものなのか?
実のところ筆者は常々疑問に感じているのです。
藤孝は真っ先に旗幟を明らかにした?
後世、順慶と藤孝の評価を大きく分けたのは、順慶が光秀の謀叛後もどっちつかずの態度を続けて、ぎりぎりまで日和見を決め込んだのに対し、藤孝はいち早く光秀に味方しないことを明らかにしたからだと、多くの人が認識しているんじゃないでしょうか。
しかし、結論から言うと日和見という点では、順慶も藤孝も全く同じと筆者は考えます。
本能寺の変後に藤孝、忠興親子がそろって髻を落とし、光秀から加勢を呼びかけられても「喪に服す」と言って出兵を断ったのは事実ですが、これはあくまで中立を示すもので、光秀に敵対の意思を示すものではありませんでした。
藤孝の中立姿勢を如実に表しているのが、息子忠興の妻で光秀の娘だった玉の処遇です。
もし、ただちに光秀への敵対姿勢を見せたというのであれば、すぐに玉を離縁して実家に送還するのが筋でしょう。
当時の武士の姻戚関係は非常に重く、時代は大きく遡りますが、鎌倉時代に北条氏と三浦氏が争った宝治合戦で、毛利季光は北条氏有利と見ながらも、妻の実家三浦氏への義理から三浦方について滅びました。
姻戚のある方に味方するのは武士の常識で、実際に忠興と同様に光秀の娘婿だった津田信澄は、妻が光秀の娘というだけで内通を疑われて殺害されており、姻戚を重視する意識は、戦国時代にあっても常識の範疇だったといえるでしょう。
なので、光秀に明確に敵対の意思を示すのであれば、玉を実家に送り返して姻戚関係を解消するのが当前ですが、藤孝はそれをしていません。
一説には藤孝は離縁するよう忠興に伝えたものの、忠興が離縁を拒絶して玉を山奥に幽閉したとも伝わりますが、いずれにせよ明確な離縁の姿勢を示していないことが重要です。
結局のところ、光秀が最終的に勝ち馬になったときのため、藤孝は玉を離縁しないことで「保険を掛けた」と言えます。
当時、同じ藤孝と丹後国を分割統治していた一色義定が、いち早く光秀に加勢したこともあり、藤孝とすれば「喪に服す」という口実で中立を保つのは、非常に良い「手」だったと思います。
光秀が敗れた場合、勝利した側に参陣しなかったとしても、「一色に備えるため動かなかった」という言い訳が成立するからです。
そして、史実は実際にそのように動きました。
洞ヶ峠の順慶は事実ではない
一方で順慶の方は、どのような動きを取ったのでしょう。
順慶の動向は、同時代史料の『多聞院日記』によると、本能寺の変の翌3日、順慶の指揮下にあった大和国衆が法華寺、大安寺、辰市近辺に着陣します。
4日には順慶指揮下の槙島城主井戸良弘と奈良盆地南部の国衆からなる南方衆が、光秀方に付いて5日には近江へ到着しました。
この4~5日にかけ、光秀は近江の平定を進めているので、順慶により派遣されたとみられる井戸と南方衆は、光秀に加勢していたとみてよいでしょう。
その一方で、5日には近江に派遣した兵を除き、順慶は山城に進軍させていた兵を大和へ帰城させています。
これは大坂にいた信孝と申し合わせた動きとされ、この時点で順慶の動きは揺らぎがあり、必ずしも旗幟を鮮明にしていません。
しかし、最小限ながら光秀に援軍を出しており、『多聞院日記』にも「順慶ハ堅くもって惟任(=光秀)ト一味と云々」と記され、この時期、順慶は光秀に味方するものと周囲に見られていました。
順慶の動きは細川藤孝とは違ってやや光秀寄りですが、京都から遠く離れた丹後にいた藤孝とは違い、光秀の軍事的圧力を強く受けていた順慶には、なるべく光秀を刺激したくないという思惑が働いたのでしょう。
周囲の有力武将の旗幟が鮮明でない中、表立って光秀に対抗すれば、真っ先に攻撃を受けて畿内で孤立する恐れもあったからです。
事態が大きく動き出すのが6月9日。
毛利との和睦を電光石火で取りまとめた羽柴軍が、いわゆる中国大返しで前日までに姫路へ軍を引き戻し、この日再び東に向かって進軍を開始しました。
この日、前日までに「秀吉迫る」の情報を察知した順慶は、光秀に呼応して準備していた河内への出陣を急遽取り止め、郡山城へ兵糧を搬入させて籠城戦の準備を始めます。
この時期、順慶が侵攻を恐れる勢力は、山城を抑える光秀しかありません。
消極的ながらも光秀への協調姿勢を見せていた順慶が、はっきりと光秀と距離を取る姿勢に転換した瞬間でした。
従来山崎の戦いの直前まで、優柔不断で旗幟を鮮明にしなかったと思われがちな順慶ですが、秀吉が畿内に接近していることを察知した早い段階で、はっきりと行動を変化させていたことがわかります。
さらに6月10日には山城、近江に派遣していた南方衆など、旗下の軍をすべて大和に撤収させました。
同日、順慶の不穏な動きを察知した光秀は、河内大和国境の洞ヶ峠に着陣(『蓮成院記録』)して順慶を威圧するとともに、重臣藤田伝五を郡山城に派遣して帰順を求めます。
そう、洞ヶ峠に着陣したのは順慶ではなく光秀だったのです。
洞ヶ峠で順慶の合流を待った光秀でしたが、すでに秀吉への帰順を決めていた順慶は、きっぱりと光秀への合力を拒絶。
やむを得ず光秀は河内から撤兵し、迫りくる羽柴軍への迎撃態勢を整えることになりました。
翌6月11日、順慶は秀吉へ誓紙を出してついに旗幟を鮮明にすると、同日、旗下の大和国衆を郡山城に集めて「血判起請」に押印。
大和一国約45万石、1万余りの兵力が、秀吉方に付くことになり、この時点で山崎における光秀の敗戦は決定したと言って過言ではないでしょう。
山崎の戦いでは、羽柴軍が総勢20,000から最大40,000とされたのに対し、明智軍は16,000。
当時1万石あたりの動員兵力は200~300とされますから、順慶の直轄18万石で動員できる最大兵力は5,400。
当時順慶旗下の大和国衆をすべて動員すれば、直轄領を含めて約45万石、13,500の兵力となりました。
仮に順慶率いる大和国衆が、1万余りの兵力で当初光秀との申し合わせ通りに河内へ進出していたら、羽柴軍は河内に陣取る順慶の兵にも1~2万程度の兵力を割かねばならず、数の上では山崎の戦いの結果もどちらに転ぶか、非常に不透明な状況になったことは間違いありません。
特に羽柴軍の総勢は26,000人程度と見積もる資料もあり、順慶が光秀に味方すれば、互角以上の戦いができる公算もあったでしょう。
しかし、順慶が秀吉に付けば兵力は羽柴軍が光秀を圧倒します。
順慶は、光秀個人へのそれまでの友誼や恩を深く感じていたでしょうが、大和一国45万石の家臣や与力たちの命運を握る立場として、確実に勝利が見込める秀吉に味方することを決断しました。
やはり、主殺しの光秀に味方するというのは、よほど明確な勝機がなければかなり高いハードルであり、確実に勝利が見込める秀吉についたのは、順当な判断といえるでしょう。
事実、光秀に呼応した武将といえば、丹後の旧領回復を狙う一色義定や、秀吉と折り合いが悪く、北近江の所領を巡って対立があった阿閉貞征、信長により追放されていた安藤守就といった信長、秀吉に不満を持つ勢力に留まりました。
結果的に、山崎の戦いが発生する2日前に、順慶は旗幟を明らかにしたわけですが、5日の段階で信孝と通じて兵を引くなど、両睨みの行動を起こしており、8~9日にかけて秀吉の接近が確認できた時点で、光秀に味方しない姿勢をほぼ明確にしています。
正式に秀吉方に付くのに、その後2日を要したのは、大和国衆の説得に時間を要したものと思われます。
順慶以外の大和国衆は、順慶指揮下にあるものの、順慶の家臣という訳ではありません。
順慶一人が秀吉に味方すると表明しても、光秀に付くべきとする国衆が万一多数派となれば、大和で順慶が孤立化する恐れもあったため、慎重に説得を重ねて、意思の統一を図ったのでしょう。
山崎の戦いで勝敗の帰趨を決したのは順慶
6月12日、羽柴、明智の両軍は、現在の大山崎JCT付近を流れる円明寺川(現小泉川)を挟んで対峙します。
翌6月13日に入っても局地的な戦闘はあったものの、朝から大規模戦闘は開始されず両軍のにらみ合いが続いていました。
この日、6月13日の日付で、織田信孝から筒井順慶に宛てた書状が残されており、この書状には6月13日から先鋒が山崎・勝竜寺へ攻め込み、信孝は翌6月14日に西岡(現京都府向日市)まで陣を進めるので、順慶も「上山城口」まで進軍するよう命令が記されていました。
また、この書状の添え状である同日付の秀吉と丹羽長秀の連署状にも、同様に翌日信孝が西岡に進出するため、順慶に山城へ出兵を命じる旨がしたためられています。
この二つの書状から、羽柴軍の構想は、順慶が大和から山城に進出して光秀の背後を衝き、6月14日にかけて山崎で迎撃態勢を取っている光秀を挟撃しようとするものだったと思われます。
数で圧倒的に不利な状況の光秀が、地の利を活かして迎撃態勢を整える中、先制攻撃を仕掛けてくるとは、秀吉にも考えにくかったのかもしれません。
しかし、光秀は13日の夕刻、突如として羽柴軍中央の中川清秀、高山右近の隊に攻撃を仕掛け、戦端を開きました。
光秀が山城、摂津国境の隘路で数に勝る羽柴軍を迎撃し、各個撃破で数的不利を覆そうという戦術を捨て、あえて自軍から出撃して地の利を捨てたのは、光秀が山崎の町と結んだ「町を戦場にしない」という約束を律義に守ったため等、様々な説が巷間伝わります。
しかし、13日の夕刻にあえて光秀が攻撃を仕掛けたのは、大和の不穏な動きを察知して背後を順慶に衝かれることを恐れ、乾坤一擲の正面奇襲攻撃に出たと考えたほうが、戦略的な蓋然性が高いように考えますがどうでしょう。
戦闘序盤、明智軍の猛攻に押し込まれた羽柴軍でしたが、やはり戦は数です。
衆寡敵せず、日没までには大勢が決して明智軍は敗走しました。
関ヶ原の戦いもそうでしたが、誰も予想だにしないほどあっけなく決戦は終了。
筒井軍が、天下分け目の戦いに出陣する機会は失われました。
翌6月14日、順慶は6千の兵を山城に派遣し、光秀側に付いていた槙島城などを接収します。
そして6月15日朝に順慶自身が千の軍勢を率いて大和を出発。夕刻に醍醐(現京都市伏見区)で秀吉と対面しました。
この醍醐における秀吉との対面で、順慶は秀吉から参陣が遅い!と激しい叱責を受けてしまいます(『多聞院日記』)。
このことも、後年、順慶が日和見を秀吉から咎められたとして、評価を下げる一因になっているかと思います。
順慶と同様、ぎりぎりまで旗幟を鮮明にしなかった細川藤孝に対しては、秀吉は7月11日付の書状で、その協力に謝意を示しているのとは対照的です。
この差は何なのでしょう。
本能寺の変が起こり、6月8日ごろまでの早い段階から、藤孝と秀吉は連絡を取り合っていた可能性が指摘されている一方、もしかすると、順慶と秀吉には、11日に順慶が起請文を送るまで、直接のやり取りがなかったのかもしれません。
早い段階で秀吉と通じていた藤孝に対し、秀吉にとって順慶は最後まで不確定要素だった可能性があります。
こういった経緯もあり、藤孝と順慶は同じように山崎の戦いに参陣しなかったにもかかわらず、藤孝が勝敗に大きな影響を与えたと大きく評価される一方で、順慶は日和見大名の汚名を被り、後世まで低評価に甘んじることになります。
しかし、客観的に見て、山崎の戦いの結果に重大な影響を与えたのは、戦場である畿内から遠く離れた丹後で身動きの取れなかった藤孝ではなく、畿内で1万近い兵力を動員できる順慶の動向であったことは明らかです。
大和国衆が光秀に付けば、秀吉の数的優位は崩れた可能性もあり、まさに順慶は天下分け目の戦いのキャスティング・ボートを握る存在だったのです。
それゆえに秀吉は、順慶の動向にヤキモキしたことは間違いありません。
順慶に対する秀吉の激しい叱責は、源平の戦いで源頼朝が兵を募ったとき、遅参してきた関東随一の兵力を誇る上総広常に「帰れ!」と一喝した姿と重なります。
実際に山崎の戦いで、戦い直後に順慶が率いた兵の数を上回る部隊は、秀吉、光秀の本隊だけであり、秀吉の怒りの大きさは、それだけ順慶の影響力が大きかったことを示していると言えるのです。
本能寺の変から山崎の合戦に至る経緯を見ても、要所要所で順慶は的確な判断と行動を行っており、状況に流されるがまま、時勢に翻弄されたわけではありませんでした。
したたかに情勢を見極め、確実に勝利者の側に付いたあたりは、流石は畿内を席巻した名将・松永久秀と大和の覇権を争い、最終的に勝利した順慶の力量の高さを示すものと言えるでしょう。
<参考文献>